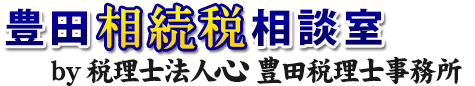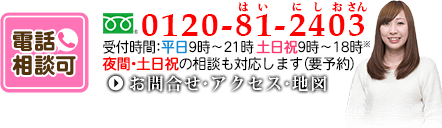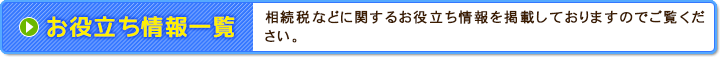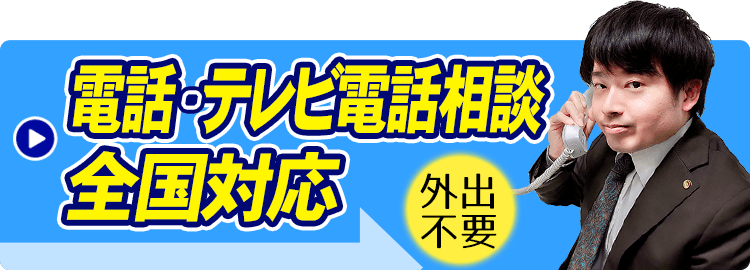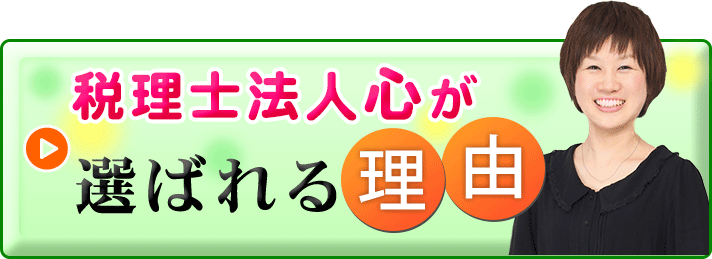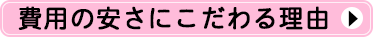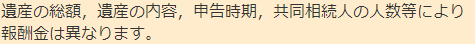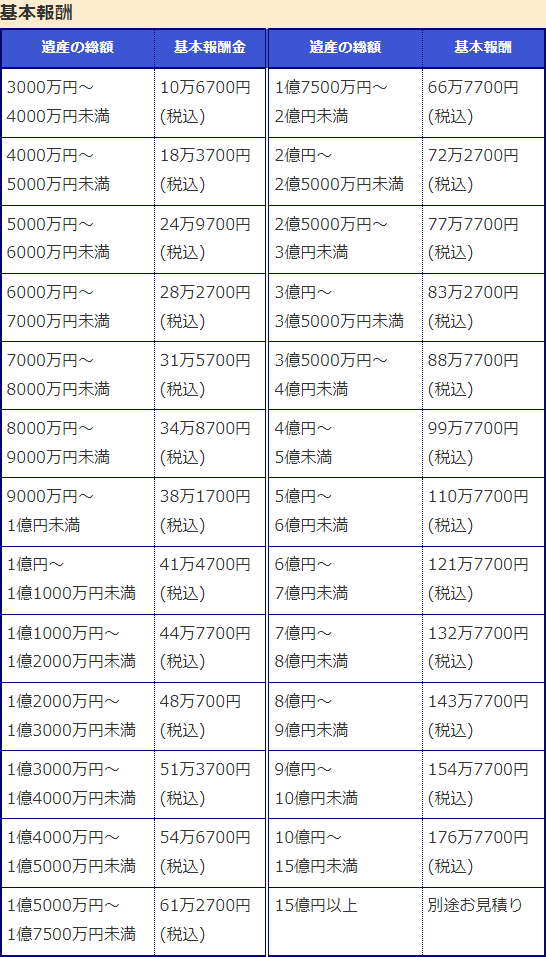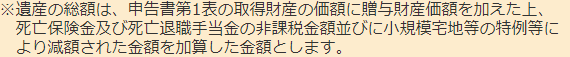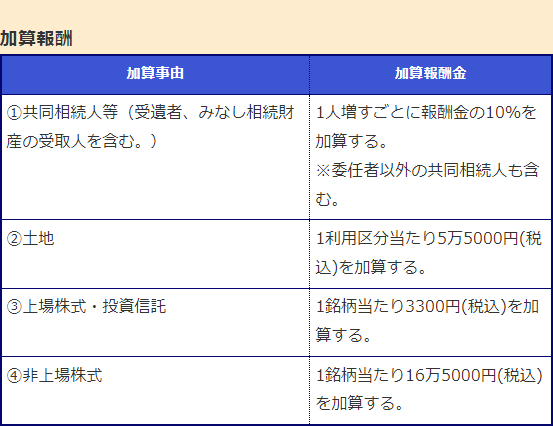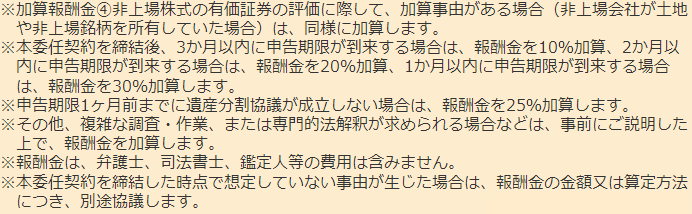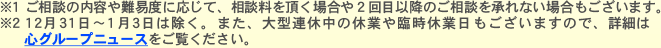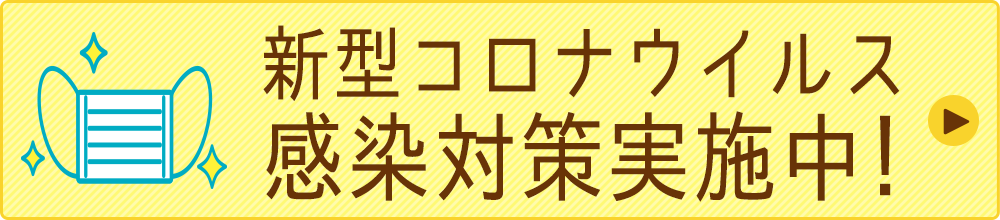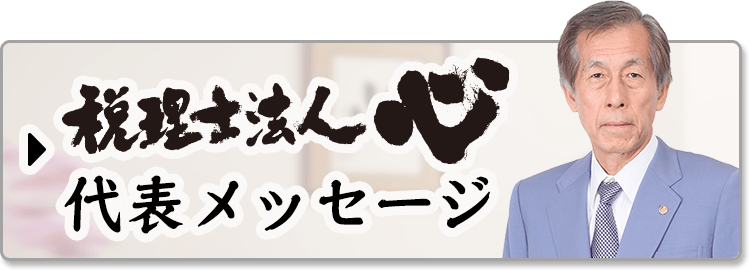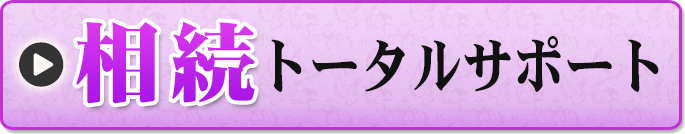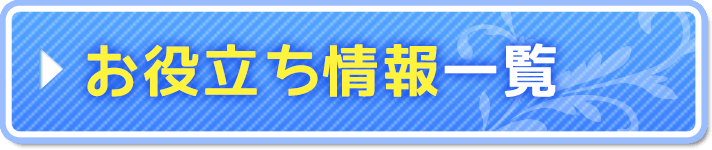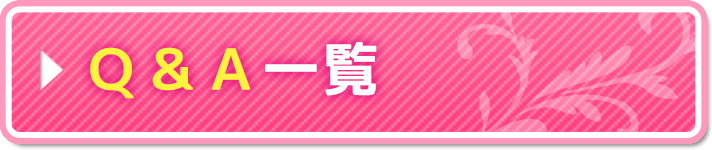住宅取得資金の特例に関するQ&A
住宅取得資金の特例とは何ですか?
住宅取得資金の特例とは、簡単にいうと、両親や祖父母から、子や孫に対する住宅を購入するための資金援助であれば、一定額までは贈与税がかからないという制度です。
この住宅取得資金の特例を利用した場合、最大1000万円まで贈与税がかからなくなりますので、非常に有用な制度です。
住宅取得資金の特例を利用するメリットは何ですか?
住宅取得資金の特例を利用することで、最大1000万円の贈与を贈与税がかからずに行うことができるため、結果として、相続税額を減らすことが可能になります。
たとえば、相続人が子の2人、相続財産が1億円の預金のみの場合、相続税は770万円かかります。
ところが、住宅取得資金の特例を使い、相続人の一人に1000万円を贈与した場合、相続税額は、620万円となり、特例を使う前よりも、150万円も相続税が安くなります。
また、住宅取得資金の特例の良いところとして、贈与税の3年内加算のルールが適用されません。
贈与税の3年内加算のルールとは、亡くなる3年前の贈与については、相続税の計算に含まれるというルールです。
そのため、亡くなる直前に生前贈与をしたとしても、相続税の計算対象となってしまいます。
しかし、住宅取得資金の特例を使った場合は、この3年内加算のルールが適用されないため、相続税の計算対象にもなりません。
住宅取得資金の特例を利用する場合の注意点は何ですか?
住宅取得資金の特例を利用して、金銭を贈与する場合の注意点として、間違った方法で贈与してしまうと、特例を受けられなくなったり、反対に相続税が高くなったりする可能性があります。
まず、住宅取得資金の特例を利用する場合、贈与税が0円であっても必ず申告が必要となります。
申告をしなかった場合、住宅取得資金の特例を使えず、贈与税がかかってきますので、注意が必要です。
次に、住宅取得資金の特例を使った結果、小規模宅地等の特例を使えず、相続税が高くなる可能性があります。
そもそも小規模宅地等の特例とは、相続税を計算するときに利用する特例で、簡単にいうと、一定の要件を満たした場合、土地の価格が最大80%減額されるという制度です。
この小規模宅地等の特例は、原則として、配偶者または同居親族だけが土地を取得した場合に使える制度なのですが、例外的に、配偶者も同居の親族もいない場合には、「亡くなった人と別居していて、かつ、3年以上借家に住んでいる親族(家なき子)」が特例を使うことができます(いわゆる「家なき子特例」と呼ばれます)。
ここで、住宅取得資金の特例をうけて、家なき子が住宅を取得した場合、小規模宅地等の特例が付かなくなってしまいます。
その結果、贈与税は支払わなくてよかったが、反対に多額の相続税がかかってしまう可能性があります。
このように住宅取得資金の特例を利用する場合は、思わぬ落とし穴もありますので、一度、相続税に詳しい専門家にご相談されることをおすすめします。
生命保険による相続税対策のQ&A 夫婦間の贈与に関するQ&A