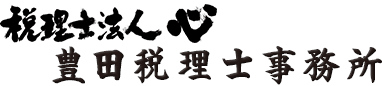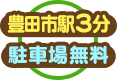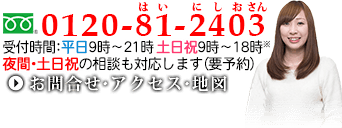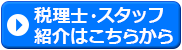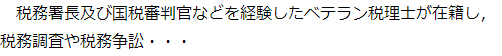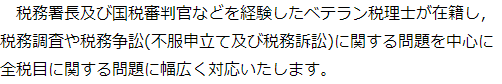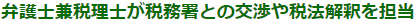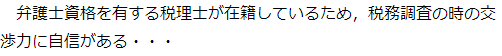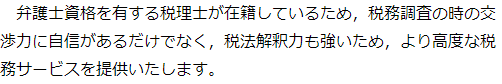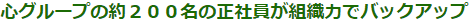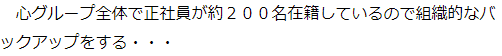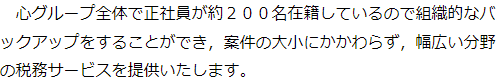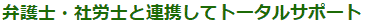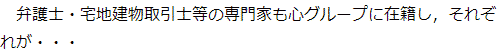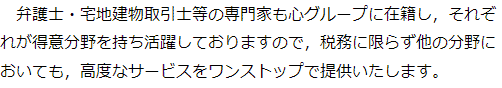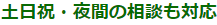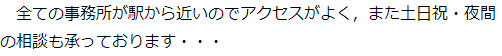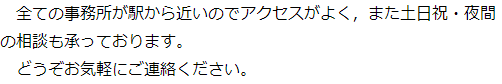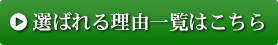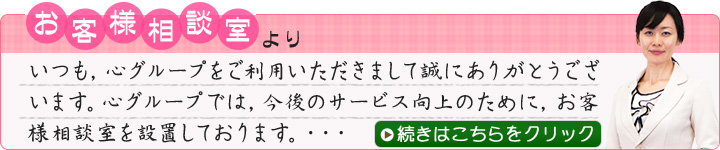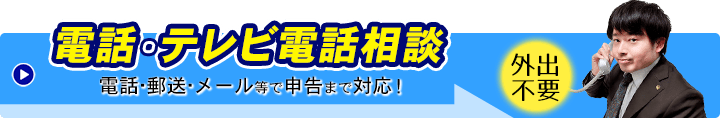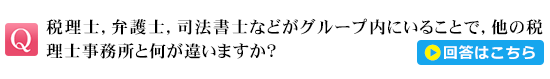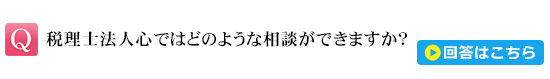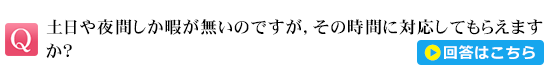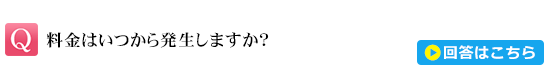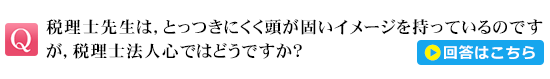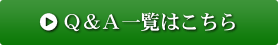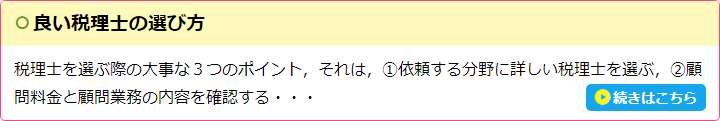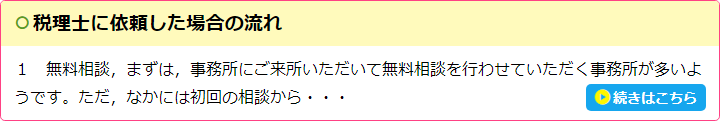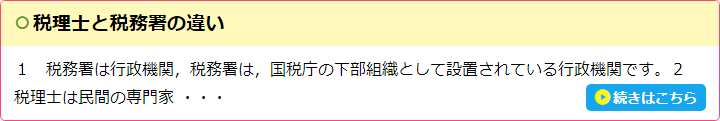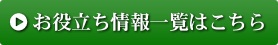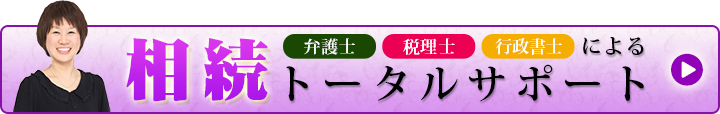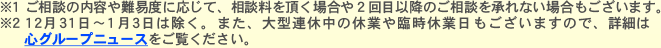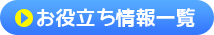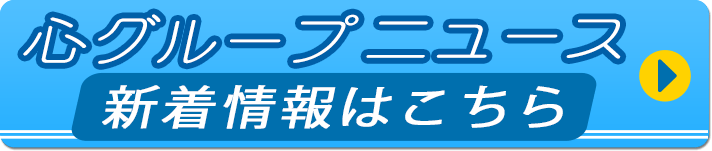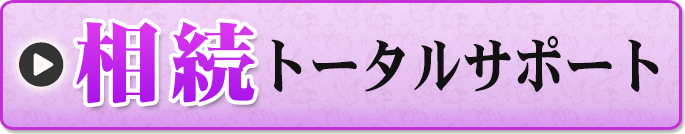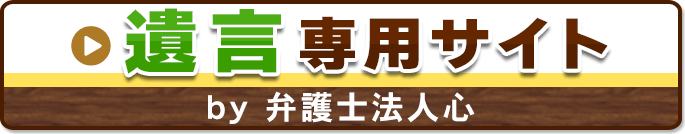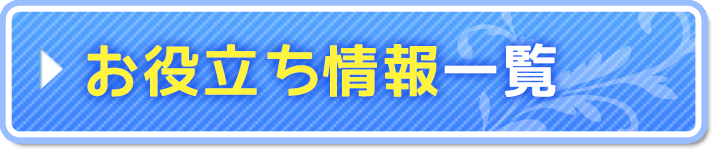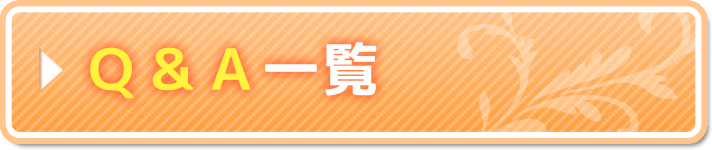税理士法人心 豊田税理士事務所とは
こちらでは当事務所の所在地をご確認いただけます。豊田市駅からも新豊田駅からも歩いてお越しいただける距離のところにあり、便利な事務所です。
税金で困ったら税理士へご相談を
1 税務相談と税務署

個人事業をしている方、土地を売却した方等は、税金について相談したいと考える方も多いです。
しかし、どこに相談すればいいのかわからない方も多いです。
税金について困ったら、税務署に相談することが一番初めに思い浮かぶかと思います。
たしかに税務署は税金を支払うための手続きについては教えてくれますが、申告書作成のためにサポートしてくれることはありません。
また、節税のことを教えてくれることはありません。
2 税務相談と税理士会や商工会議所
税理士会や商工会議所で税務相談を開催している場合もありますので、そういったところに相談する方もいらっしゃいます。
基本的に、無料で相談にのってもらえます。
ただし、30分から1時間程度の時間制限があったり、相談にのってもらえる人数に制限があったりします。
また、相談内容に制限がある場合もありますので、事前に電話やホームページ等で確認することをおすすめします。
3 税務相談と税理士
そのため、じっくり相談にのってもらうには、税理士に相談することをおすすめします。
最近では、無料相談をしている税理士事務所もありますので、事前に問い合わせてみましょう。
相談内容によっては、その税理士が得意としていない場合もありますので、事前にどういった税金に関する相談か、また、その税理士が得意としているのかということを問い合わせておくことが重要となります。
税理士に相談するタイミング
1 できる限り早い段階で税理士に相談した方が安心

どのタイミングで税理士に相談すべきか悩んでいる方も多いと思います。
できる限り早いタイミングで、ご相談いただいた方が、準備にも時間をかけられますし、節税等の手段を検討する時間もとれます。
悩まれている方は、お気軽にご相談ください。
2 事業を開始する場合の税理士への相談のタイミング
個人事業を開始するとき、会社を新しく設立するときに税理士にご相談いただくことが多いです。
これまで事業をしたことがない方の中で、税金について詳しいという方はほとんどいらっしゃいません。
税理士に相談して、どのような帳簿を作成すればいいのか、そもそも申告とはどのようなものなのかなどを相談する必要があります。
事業開始から税理士が関与することで、税金関連のことを税理士に任せることができ、事業主の方は、事業に集中することができます。
3 確定申告時期が近付いてきた場合の税理士への相談のタイミング
確定申告時期が近付いてくると、どのように申告すればいいのか、何を書類としてそろえればいいのかという問い合わせが増えます。
申告期限ぎりぎりに相談する場合で、帳簿すら作成していない場合には、申告が期限内にできないこともありますので、注意が必要です。
また、税理士に事前に相談していなかったために、取っておくべき領収書を廃棄してしまっていたという方もよくいらっしゃいますので、税理士に相談するタイミングはお早めをおすすめします。
また、一般的に税理士事務所は、12月ごろから年末調整の手続きのために忙しくなり、年明けからは顧問先の確定申告の準備のためにさらに忙しくなることが多いです。
そのような繁忙期になってしまえば、税理士に相談することが難しくなることすらありますので、所得税の確定申告の場合には、余裕をもって11月より前には相談することをおすすめします。
4 所得税や法人税の場合の税理士への相談のタイミング
所得税や法人税の申告のためには、普段から記帳をしっかり行っていることが重要です。
そのため、毎日の記帳に関して、疑問や不安なことがあれば、そのタイミングで税理士に相談することをおすすめします。
また、年末又は期末には、どのような申告書を作成するのかが問題となってきます。
そのため、申告書の作成及び提出をする前には、税理士に相談することをおすすめします。
所得税の申告期限は毎年3月15日、法人税の申告期限は期末から2か月後です、この申告期限の直前に初めて税理士に相談するのでは、申告書の作成期間を十分に確保することができませんので、余裕をもって相談をするのが良いといえます。
5 相続税の場合の税理士への相談のタイミング
相続税の申告書作成のためには、相続財産に関する資料の収集、整理、検討に十分な時間が必要になります。
相続税の申告書の提出及び納付の期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内となっていますが、申告書作成のために十分な準備をするには、できる限り早く税理士に相談をするのが大切です。
税理士に相談するタイミングは早ければ早いほどいいです。
ただし、申告期限が迫っている場合でも一旦仮の申告をして、その後、申告し直すということも考えられますので、税理士に遠慮することなく、とにかく相談してみるのが重要です。
6 贈与税の場合の税理士への相談のタイミング
贈与税は、比較的、申告書作成に必要なための期間は短いことが多いです。
しかし、贈与税が多額になり、準備に時間を要する可能性があるので、早めに相談することが望ましいです。
納税額が多くなれば、納税資金を準備する時間も必要なので、納税額をある程度確認しておく必要があるという観点からも、早めに相談することが望ましいです。
また、贈与税は、減額のための特例が多く、特例の適用のための検討や書類の準備が必要になることもあります。
そのため、贈与を実際にする前に税理士に相談することが望ましいといえます。
7 税務調査の連絡が税務署からあった場合の税理士への相談のタイミング
税金に関する何らかのトラブルが生じた直後、つまり、税務調査で何かしら申告書の不備を指摘される可能性が高まったときも、ご相談いただくことが多いタイミングです。
税務署から連絡があれば、できる限り早くご相談いただき、税理士が帳簿や申告書をチェックしたうえで、申告に臨めば、税務署の前で、不用意な発言をするといったリスクは下げることができます。
税理士法人心の強み
1 依頼者にワンストップで様々なサービスを提供できる

税理士法人心は、弁護士法人、社会保険労務士法人、保険代理店会社、行政書士法人など、関連業界の関連会社と一体的に連携しているので、総合的なサポートを実現できます。
また、数多くの専門家・スタッフがおり、組織的なバックアップをもって、様々な税分野及び関連分野でのサービスを提供させていただくことができます。
2 多数の税理士が在籍しているので、専門性を高められる
多くの税理士が在籍しているので、一人が全ての分野のスキルを少しずつ高めていくのではなく、特定の税理士がそれぞれの得意分野のスキルを高めることができます。
全国で相続税の申告件数は年間13万件程度であるのに対し、税理士登録している人数は約8万人であることからすると、一般的に税理士は、相続税の経験を積みにくいといわれていますが、税理士法人心では、特定の税理士が集中的に相続税の経験を積み、得意分野のスキルを高めています。
3 税理士兼弁護士
弁護士資格をもっている税理士が在籍しているため、税務調査の際の交渉力に長けており、より高度な税務サービスを提供いたします。
税法と税理士業務は、切り離せない関係にありますので、税法解釈力の高さが提供できる税務サービスの質の高さにつながります。
4 お客様のご都合に柔軟に対応します
税理士法人心は、お客様の利便性のため、すべての事務所が駅から近くアクセスがよい場所に事務所を構えています。
また、平日夜間だけでなく、土日祝日の相談も承っております。
お気軽にお問い合わせください。
税理士に相談すべきケース
1 税理士に相談すべき場合

経費の節約のために、税理士に確定申告書の作成及び申告を頼まずに、自分自身で帳簿や申告書を作成し、申告及び納税をしている個人事業主の方もいらっしゃると思います。
簡単な帳簿や申告書であれば、自分自身で作成した方が費用もかからないためよい場合もありますが、税理士に相談した方がよいケースもあります。
2 事業規模の大きさ
事業規模が小さい場合は、取引数が少ないことも多く、複雑な税務処理を必要とする場面が少ないので、個人で帳簿を付けたり、確定申告をすることも可能です。
しかし、事業規模が大きくなると、取引数が多くなる傾向にありますし、複雑な税務処理が必要となる場合も増えます。
また、税務処理をミスした場合にその金額が多額になる傾向にありますので、税理士に相談することをお勧めします。
具体的には、年間の売上が1000万円を継続的に超えるようになってきた場合には、事業規模が大きく、税理士に相談すべきケースということになります。
年間の売上が1000万円を越えると、2年後から納付すべき消費税の金額を自分で計算して、確定申告をする必要がでてきます。
消費税の計算を正確にするためには消費税法の知識が欠かせないため、所得税の確定申告をするよりも難しいといえます。
また、年間の売上が1000万円を越えるほどの事業規模になると、税務調査が入る可能性が高まります。
3 本業が忙しい方
日々の業務で忙しく経理業務ができない場合は、申告書の作成だけでなく、税理士に依頼をして、記帳代行をお願いすることをお勧めします。
税理士に依頼せず自分でやろうと考える方もいらっしゃいますが、経理業務は売り上げと直結する業務ではないため、ついつい後回しになりがちです。
数か月領収書をためてしまった結果、確定申告の時期と繁忙期が重なってしまったということになれば、本業に集中できないという事態にもなりかねません。
税理士に払う費用よりも浮いた時間で本業に集中して、売上を伸ばした方がよい場合もあります。
4 帳簿作成や申告書作成に関する知識がない方
帳簿や確定申告に関する知識がほとんどない、また、数字に弱いという方は、帳簿や確定申告書の作成に膨大な時間をかけることになりますし、間違っていれば税務調査の際に指摘され、ペナルティを受ける可能性もあります。
現在、帳簿や確定申告書作成に不安を抱えている方は、税理士に相談することをお勧めします。
税理士に相談して依頼するまでの流れ
1 まずは税理士へ相談

事業を始める予定の方、既に事業を始められている方、これまで自分で確定申告を行ってきたが不安がある方、白色申告から青色申告に切り替えたい方など、これから税理士を探さなければならない、あるいは税理士への依頼を検討しているという方がいらっしゃるかと思います。
その際、どのような流れで税理士に相談し、依頼すればいいのかよく分からないという方もいらっしゃるかもしれません。
ここでは、税理士に相談する流れを説明していきたいと思います。
2 税理士に相談する前の準備
税理士に相談する前には、事業の状況を確認できる資料についてご準備をお願いします。
まず、顧問料や確定申告報酬等の費用は、事業の売上や経費の額、個人事業なのか法人なのか、従業員の人数、給与計算まで希望されるのか、また定期的な訪問を望まれるのか等によっても異なります。
事業の状況を確認することができれば、具体的なお見積もりをすることができます。
ご相談内容も一般的な相談をすれば、一般的な回答しか得られませんが、自分の事業の現状や過去の申告状況をもとに具体的に相談することで、より充実した相談をすることができるかと思います。
税理士としては、過去の申告書数年分、総勘定元帳、現在申告している期の請求書、領収書等、現在の売上や経費等が分かる書類のご持参をお願いすることが多いです。
何が必要かは、事前に税理士に確認すれば教えてくれるため、聞いてみてください。
3 税理士への相談
相談の進め方は、税理士によって様々です。
よくあるのは、まずいつからどのような事業をしているのかを確認し、過去の申告書や決算書類、帳簿書類等を確認したうえ、現在の状況や課題、今後の事業展開の予想・ご希望等をお伺いします。
また、税理士事務所に対して、確定申告書類の作成、年末調整、記帳代行までご希望されるのかなど、どのような対応を希望されているのかを確認させていただきます。
一度の相談で疑問点が解消しなかったり、新たに疑問点が出てきたりした場合は、再度税理士へご相談ください。
領収書の編綴の仕方など、些細なご質問でも大丈夫です。
税理士と顧問契約をする場合には、長いお付き合いになることがほとんどです。
納得できるまでじっくりと相談することをおすすめします。
4 税理士に依頼
相談後、税理士に依頼したいと考えた場合には、その旨を税理士に伝えます。
税理士業務の範囲や費用について協議し、双方同意ができれば、契約が成立し、正式に契約書を取り交わすことになります。
税理士選びのポイント
1 税理士の選び方

税理士といっても、得意分野は人それぞれ異なります。
法人の会計・税務に詳しく経営アドバイスが得意な税理士、個人向けの確定申告をスピーディーにこなすのが得意な税理士、相続税申告や生前対策を得意とする税理士など、様々な税理士がいます。
また、税理士に頼める仕事としては、記帳代行、記帳指導、決算業務、税務申告業務、税務調査立ち合いだけでなく、資金繰り、節税対策もあります。
このように、税理士は幅広い業務を取り扱うことができ、それぞれ得意分野がありますので、税理士に依頼をする際は、依頼内容を得意としているかどうかを確認することをおすすめします。
2 税理士との相性も大切
法人税、所得税の顧問税理士を依頼する場合には、基本的に長いお付き合いになることが多いです。
依頼することを決めた人だけでなく、その子供の代までお付き合いすることも多いです。
そうすると、税理士との相性が大切ですし、気軽にいろいろといつでも相談できる税理士を選ぶことをおすすめします。
3 税理士に何を頼むのかによって費用が異なります
税理士に依頼する際は、何を頼むのかをしっかり考えるとよいと思います。
自分で帳簿をつけることはできるので、税理士に帳簿作成を頼むのではなく、年に1回、確定申告書のチェック及び申告だけを頼み、税理士報酬を安く抑えるということも可能です。
税務申告だけでなく、会計・経営のコンサルティングまで頼むことも可能ですが、費用は高くなる傾向にあります。
自分の事業を進める上で足りないことと費用との兼ね合いから、どういったサービスをどの程度の報酬で頼むかを検討していただくとよいかと思います。
また、税理士に最初に相談する際に、見積もりを取ることも重要です。
相見積もりをとるときは、条件を同じにしておくと比較するのが簡単なのでおすすめです。
税理士の探し方
1 税理士を探すときのポイント
個人事業主の方が税理士に顧問を依頼したいという場合、どのようなポイントに気をつけて、税理士を探せばいいのでしょうか。
以下では、どういった税理士に依頼すべきか、良い税理士の特徴を説明していきたいと思います。
2 相性が良い税理士を探す

税理士との人間的な相性が悪ければ、どれだけ優れた思考と知識を持っている税理士だとしても十分なコミュニケーションが取れず、税理士に対して十分に質問できないと思われます。
税理士は、あくまでも税務面からサポートする存在です。
実際に、事業を行ってお金を稼ぐのは個人事業主です。
税理士が優れた相談役となるのか、ただ書類作成をするだけの存在となるのか、最終的には税理士との相性によって決まります。
3 税理士をサービス業と考えている税理士を探す
税理士の中には、先生と呼ばれ慣れて、自分を偉い存在だと思い込んでしまっている人もいます。
このような税理士は一見頼りがいがあるように見えることもありますが、税理士をサービス業と考えている税理士と比較して、税務サービスが不十分であることも多いです。
4 日々の勉強を欠かさない税理士
税制は毎年改正され、知らなければ税金の面で大きな損をすることもあり得るような改正もたくさんあります。
そのため、日々の勉強が欠かせません。
税理士でない方からすると驚かれるかもしれませんが、日々の勉強を怠り、改正についていけてない税理士もいるのが現実です。
税理士には、義務研修が年間36時間課されており、各税理士が義務研修の最低限の受講時間を達成したかどうかは、日本税理士連合会のサイトで確認できますので、確認してみるのもおすすめです。
税理士の平均年齢は60代ですが、年齢の高い税理士だからといって毎年の改正に対応できていないとも限りませんし、年齢の分、豊富な知識経験を有している方も多いです。
若い税理士も年配の税理士も良いところと悪いところがあります。
そのため、どちらの年齢層の税理士も所属していて、お互いに切磋琢磨しているような税理士事務所が理想といえます。
5 レスポンスが早く様々なことに柔軟に対応してくれる税理士
税金は期限を守ることが非常に大切です。
最たる例は、確定申告期限ですが、青色申告の承認を受けるための期限、消費税の計算方式で簡易課税を選択するための期限など、税額に大きく関わってくる期限が沢山あります。
そういった期限があるので、税理士のレスポンスが早いことは非常に大切です。
また、税金の計算しかせず、それ以外のことには関わらない税理士もいます。
経営相談や節税アドバイス等、柔軟に色々なことへ対応してくれる税理士がおすすめです。
また、税務以外のことについて解決手段が示せないとしても、信頼できる弁護士や司法書士を紹介してくれるような顔の広い税理士もおすすめです。
6 お気軽にご相談ください
税理士法人心は、弁護士や社労士等とも連携していますので、様々なニーズに対応することが可能です。
また、それぞれの分野において、集中的にその分野を取り扱う税理士がいますので、法改正や最新の動向についても把握しています。
税の問題でお悩みの方は、お気軽に当法人へご相談ください。
税理士に依頼するメリット
1 不動産に強い税理士に依頼するメリット

不動産の売却をした場合には、譲渡所得税が課税されます。
所得税の税率は、長期譲渡所得の場合は15%、短期譲渡所得の場合は30%です。
譲渡所得は値上がり益に課税されるので、不動産を購入した際の価格を証明することができれば、売却金額から購入金額を差し引いて、所得の計算をします。
購入金額がわからない場合には、概算取得費として、売却金額の5%を取得として差し引くことができますが、かなりの譲渡所得が発生してしまい、税金も高くなってしまいます。
通常、購入金額は売買契約書により証明しますが、かなり前の売買だと契約書がない場合もあります。
売買契約書がなかったとしても、分譲業者から不動産を購入している場合には、分譲業者が保管している書類から購入金額を推測することがあります。
また、登記簿の乙区欄記載の住宅ローンの金額から購入金額を導き出すこともあります。
さらに、注意しなければならない点はあるものの、不動産が存在する地域によっては、市街地価格指数を参照して、購入価格を推測することもあります。
このように、不動産に強い税理士であれば、様々な手段、資料から税金が低くなるように検討して、確定申告を行うことができるというメリットがあります。
2 相続税に強い税理士に依頼するメリット
相続税は、詳しい税理士とそうではない税理士で申告書の内容が大きく異なる場合があります。
そうなると納付する相続税額も大きく変わってきます。
そのひとつの原因としては、土地の評価方法で大きく変わることがあるためです。
例えば、間口が狭く細長い通路がある旗竿地の場合、隣接する近似整形地の奥行価格補正率が整形地全体の奥行価格補正率よりも大きい場合には、単に不整形の地積を間口距離で除して算定した奥行距離をもとして、求めた整形地補正率により評価する方法よりも評価を下げることができることも多いです。
また、相続税は減額のための特例がいくつもあります。
特例を使うかどうかは、納税者の判断にゆだねられるので、使えるはずの特例を見逃しても税務署から教えてくれることはありません。
このように、税理士によって、申告内容が大きく異なることもありますので、相続税に詳しい税理士に依頼すると、できる限りの評価の減額や特例の適用をすることで相続税を減らすことができるというメリットがあります。
税理士の専門分野
1 税理士の取り扱うことができる分野

税理士であれば、すべての税目に関する税務業務を行うことができますし、すべての業種について税務業務を行うことができます。
つまり、普段、個人の所得税の確定申告ばかりしている税理士でも、依頼があれば相続税の申告をすることができます。
また、顧問先に美容院が多い税理士でも、接骨院の顧問をして、所得税又は法人税の申告をすることもできます。
しかし、単に業務ができるということと、その分野・その業種に精通し、適切なアドバイスができるということは別問題であるという点に注意が必要です。
2 税理士でもすべての分野に精通しているわけではない
税理士試験を受験し税理士になるためには、会計学に関する科目を2科目と税金に関する科目を3科目に合格する必要があります。
全ての税目を勉強する必要はありませんし、どの科目を選択するかは、一定の決まりがあるものの、ある程度自由に選択することができます。
そのような仕組みであるが故、例えば、相続税の科目を一切勉強せずに税理士になることも可能となってしまいます。
特に相続税は、ほかの税目に比べ民法に対する理解も必要となるため難易度が高く、避けられる傾向にあります。
もし、税理士資格を取得した時点で特定の科目しか勉強していないようであれば、得意・不得意の税務分野ができてしまうことにもなりかねません。
3 多くの実務経験を積めるかも重要
さらに、税理士になったあとにどれだけの実務経験を積めるかどうかも重要になってきます。
相続税を例に挙げると、年間の申告件数と全国の税理士の人数から計算すると、税理士一人当たりの申告件数は2件以下となっています。
年間でたった数件しか申告を行わない税理士が、相続税を専門分野といえるレベルまで習熟するにはかなりの時間がかかるかと思います。
専門分野として習熟していなければ、処理が遅く、知識や経験が不足して間違った処理または適切でない処理をしてしまう可能性もあります。
このことから、税金について税理士に相談する際は、相談したい内容を得意としており、日頃から数多くの案件を取り扱っている税理士を選ぶことが大切であるといえます。
税理士に依頼した際の料金
1 税理士業務と税理士報酬

税理士報酬は、かつては、税理士法のもと税理士会の報酬規程が定められていました。
しかし、現在では、その報酬規程は廃止され、各税理士事務所は、料金を自由に決めることができることになりました。
今では、事務所ごとに税理士報酬が異なりますし、料金表についても何に着目して税理士報酬を算出するかも自由となっています。
例えば、相続税は、遺産総額の1%が相場といわれていますが、税理士事務所によっては、遺産の総額に加え、土地の数や共同相続人の人数等を参考に、税理士報酬金額を決めることもあります。
2 税理士の報酬の定められ方
税理士報酬は、通常、扱う金額や作業量を考慮して決まることが多いです。
扱う金額が大きくなればなるほど、税金の額も大きくなり、それに伴い責任も重くなるからです。
作業量は、毎日の仕分けの数、領収書の枚数、従業員数等を基準にして判断し、作業量が多ければ多いほど税理士報酬が高く設定されていることが多いです。
3 税理士の報酬の内訳
法人税の申告の場合の税理士報酬であれば、顧問料、記帳代行料、決算料のように内訳を分けることができます。
毎月の顧問料、記帳代行料に加え、決算料を決算の時に請求することもあれば、毎月の顧問料の請求の中に記帳代行料を含め、決算の時には何も請求しないという場合もあります。
また、ほかにも年末調整、各種税務関係書類の作成のために、別途税理士報酬を請求する税理士もいます。
その税理士事務所の報酬体系次第ですが、年間にいくら税理士報酬がかかるのかということを比較した方がいいといえます。
4 税理士業務と税理士報酬の確認
税理士報酬の金額だけを確認するのではなく、見積もりの税理士報酬でどこまでの税務業務を依頼することができるのか、ということも確認が必要です。
目先の顧問料のみの金額だけで判断してしまうと、実は依頼したかった内容が顧問料に含まれておらず、別途料金が発生することになってしまうため、年間の税理士報酬が高額になってしまったという事態を招いてしまうかもしれません。
どこまで税務業務を依頼するのか、その範囲だとどれだけ年間の税理士報酬がかかるのかをしっかりと税理士に相談することをおすすめします。
税理士に相談をする際に大切なこと
1 税理士を探す際に大切なこと

税理士に相談する前提として、税理士を探す必要があります。
探し方としては、大きく分けて、自分で探すか、知人の紹介で探すという二つの方法があります。
自分で探す場合は、近くの税理士の看板や広告を見て探す、インターネットで税理士事務所のホームページを見て探す、インターネットで税理士紹介サービスを利用する、税理士会の無料相談で税理士を探す等の方法が考えられます。
これらの方法で探した税理士の中から、実際にどの税理士に相談・依頼をするか決める際は、ご自身の依頼しようとしている税分野に詳しい税理士かどうか確認する必要があります。
なぜなら、すべての税目に精通している税理士はほとんどいないからです。
所得税、法人税、相続税などの様々な税分野があり、それぞれの専門的知識の習得に加えて、実務経験を積むことはなかなか困難な場合があります。
特に、相続税申告については、年間約10万件の相続税申告件数がある一方、税理士の人数は約7万人もいるので、人数からざっと計算すると、年間で1、2件の申告しか行っていない税理士がほとんどなのが実情です。
2 実際に相談をする際に大切なこと
実際に相談をする際には、依頼したい内容や、予算感をお伝えください。
何をどこまで税理士に任せるかによって、税理士報酬が異なってくるためです。
報酬が安いという理由で選んだものの、サービスの範囲が狭く後悔する方もいらっしゃるようですので、後悔のないように事前にしっかりと確認することが大切です。
加えて、税理士と相談をする際には、相性についても確認しておくとよいです。
税金関係のことを質問する機会が多くなってくるため、些細なことでも質問しやすい関係になれそうかというのは、非常に重要です。
3 相談後に気を付けておきたいこと
実際に相談をして、税理士と契約したのち、業務が始まりますが、当初相談した内容どおりかの確認をするようにしてください。
万が一、業務開始後に、サービスの内容について変更をしたいと思ったら、税理士に相談してみるのがよいかと思います。
税理士に相談する際に用意するもの
1 税理士との相談と資料

税理士は税金についての専門家で、毎月の記帳業務や会計業務、年一回の確定申告を任せられる存在です。
税金関係の相談の際には、税理士に会計書類等を見せることによって、スムーズに相談が進みます。
資料がないと相談できないというわけではありませんが、資料がなければ抽象的な税金の話で終わってしまう可能性が高いです。
なお、税理士に何を依頼したいかによって、税理士に相談する際に用意すべき書類は異なります。
2 所得税、法人税の相談をする場合に用意すべき書類
確定申告に関する相談を具体的にする場合には、収入や給与明細、事業売上に関する資料、賃貸収入に関する書類といった所得関係の書類を準備しておくと役に立ちます。
また、経費に関する資料、法人の基本的な資料を用意することをお勧めします。
法人の場合であれば、定款、商業登記簿謄本、直近の申告書類、総勘定元帳などがあれば、税理士との相談を進めるうえで、重要な資料となります。
また、現金出納帳、売上帳、売上及び経費の入出金に使用している通帳の写し、請求書や領収書があれば、より具体的な税金の相談になる可能性が高いです。
さらに、前年の確定申告書や青色申告承認申請書といった過去の申告書に関する資料があると、スムーズに相談ができます。
3 相続税の相談をする場合に用意すべき書類
相続税は相続財産にかかってくるものであり、相続人が納める税金です。
そのため、相続関係の確認のために、被相続人の出生から死亡までの一連の書類や相続人の戸籍があると、相続人の人数が確定し、基礎控除額を計算することができ、具体的な相談をすることができます。
また、相続財産の確認のために、不動産の情報が記載されている固定資産税評価明細書、預貯金の情報が記載されている通帳等、有価証券の情報が記載されている取引残高報告書等、といった書類とともに財産の一覧ががあるとスムーズです。
4 用意する資料が分からない場合
税理士に相談する内容によって、用意すべき書類は変わりますし、何を用意するべきかわからない場合もあると思います。
相談する際には、事前に税理士に必要な書類を確認して準備することが重要となります。
税理士を紹介してもらう際のメリットと注意点
1 税理士の探し方と紹介

税務サービスを受けるために税理士を探そうとしたとき、どのような方法があるのでしょうか。
インターネットで「税理士 豊田」と検索して税理士を探す方もいれば、駅の待ち時間にたまたま看板を見て税理士を選ぶ方や、知り合いに税理士を紹介してもらうこともあると思います。
この記事では、知り合いや友人の紹介で税理士を探す場合のメリットと注意点を説明していきたいと思います。
2 税理士を紹介してもらうことのメリット
友人から税理士を紹介してもらう場合には、ひどい税理士にあたることは少ないであろうというのがメリットといえます。
友人も紹介する以上、少なくとも自分にとってはおすすめのできる税理士であるはずなので、一定レベル以上の税理士を期待できるといえます。
信頼できる税理士を紹介していると思いますので、初対面であっても安心して相談できるかと思います。
事前に、その友人に、税理士の人となりの確認をすることもできますので、緊張せず落ち着いて相談できる可能性が高いのではないでしょうか。
3 税理士を紹介してもらう場合の注意点
税理士によって、それぞれ得意の税分野がありますし、提供するサービスは様々です。
その友人にとって素晴らしい税理士だったとしても、ご自分が頼みたい税分野、税務サービスと一致していない場合もあり得ます。
例えば、相続税が得意であり年に100件以上の申告をしている税理士を紹介してもらっても、法人の顧問税理士を探している場合には、ニーズが合っていないことになります。
また、料金体系も様々です。
友人にとってリーズナブルに感じていた料金が、紹介を受けた側にとっては安くなかったり、頼みたいサービスによって料金が加算されたりすることもあります。
友人は丸投げですべて税理士に任せれば多少税理士報酬が高くても問題ないと考える方だったのに対し、紹介を受けた側にとってはできるかぎり税理士に任せるのではなく、自分でできることは自分で対応し税理士報酬を安くしたいと考えていたという場合もありえます。
こういった得意分野、料金体系、提供されているサービス内容の不一致はどうしても起こる可能性があります。
そういった場合に、紹介された手前、断りにくいというデメリットがあります。
ただ、ニーズとの不一致があれば、断っても税理士に悪い心証を持たれるということはあまり考えにくいですし、丁寧に理由を説明して断れば紹介をしてくれた友人の顔をつぶすこともないでしょうから、断るという選択をすることも大切かと思います。
被相続人が事業をしていた場合は税理士にご相談ください
1 相続と準確定申告

被相続人が事業を行っていた場合には、その年の1月1日から亡くなった日までの売上と経費を計算して、準確定申告をする必要があります。
準確定申告の申告期限及び納付の期限は、相続開始日の翌日から4か月後です。
相続開始日から申告期限まであまり時間がありません。
万が一期限に遅れてしまったり、申告をしなかったりすると、ペナルティが課されるおそれがありますので、注意が必要です。
2 相続と青色申告の承認申請
被相続人がマンション経営等をするなどして不動産所得を得て、確定申告していた場合を考えます。
この場合、相続人がマンションを相続すれば、不動産所得が発生しますので、被相続人と同じように不動産所得を確定申告する必要があります。
確定申告の方法の中に、青色申告というものがあります。
青色申告の場合、複式簿記に基づき帳簿をつけるなどの一定の要件のもと最大65万円の控除を受けることができます。
青色申告にはこのようなメリットがあるため、被相続人が青色申告をしていた場合、相続人も青色申告をして、最大65万円の控除を受けたいと考えるのが通常だと思います。
しかし、注意していただきたいのは、被相続人が所轄税務署長から承認を得ていた青色申告する権利は被相続人に帰属するものであり、相続人にその権利が相続されることはないということです。
相続人が青色申告をしたいと考えた場合には、相続人自身が青色申告承認申請書を所轄税務署に提出する必要があります。
3 相続と青色申告承認申請書の提出期限
相続人が青色申告承認申請書を提出する場合の期限は、被相続人が亡くなられた日がいつであるかによって異なってきます。
被相続人が1月1日から8月31日までに亡くなられた場合には、相続開始日から4か月以内に提出する必要があります。
この相続開始日から4か月以内というのは、準確定申告の申告期限と一致します。
被相続人が9月1日から10月31日までに亡くなられた場合には、その年の12月31日までに提出する必要があります。
被相続人が、11月1日から12月31日までに亡くなられた場合には、翌年の2月15日までに提出する必要があります。
このように、提出する必要があるというだけでなく、準確定申告の提出期限よりも短い期限が定められていることがあることにも注意が必要です。
4 青色申告のメリット
青色申告の最大のメリットといわれているのは、帳簿の作成等の比較的簡単な条件を満たすことで、10万円又は65万円の控除を受けられるということです。
また、個人事業の場合、家族に払った経費は経費とすることはできないのが原則ですが、青色申告であれば、一定の要件のもとに全額経費とすることができます。
さらに、白色申告では、赤字を繰り越すことはできませんが、青色申告であれば、赤字を翌年以降3年間繰り越すことができます。
その他にも青色申告には、優遇措置がとられています。
5 被相続人が事業を行われていた方はご相談ください
特に、税理士に頼まずに不動産収入を本人が確定申告しているという方の場合は、制度の見落としがあり、思わぬ損をする場合があります。
そのため、今まで税理士に相談したことはなかったという方ほど、税理士に相談することをおすすめします。
当法人は、駅の近くに事務所を構えておりますので、お気軽にご相談ください。
様々なテーマの情報を掲載しています
こちらには、税理士へのご相談をお考えの方に向けて、お役に立つ情報を掲載しています。こちらの他にも、当サイトには様々な情報を掲載しています。